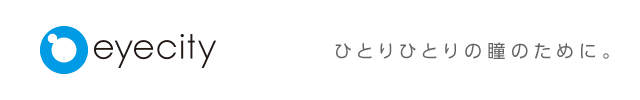- コンタクトレンズのアイシティ トップ
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 自信がなさそうに見える人ってどんな人? ビジネスに役立つ心理学
心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 心理学者 / 臨床心理士
- 植木理恵
自信がなさそうに見える人ってどんな人? ビジネスに役立つ心理学

説得力を感じる人と信憑性を問われる人。その違いは?
何気ない話をしている時にも「この人は説得力がある」と感じるときと、反対に「この人はなんとなく信憑性がない」と思わされるときがありますよね。一般的に、自信を持って話す人には説得力を感じやすいものですが、自信がなさそうに見える人はせっかく良い内容を話していても「うーん。本当に?」と疑われやすい傾向があります。なぜなら、話し手本人が自信を持って堂々として見えるときは、聞く側にも「じゃあ一旦は相手を信用してみようか」というモチベーションが働きやすくなります。心理学では、これを動機エンハンシングといいます。
しかし、話し手本人に自信がなさそうな場合は、「え?この人大丈夫なのかしら」と聞く方を不安にさせてしまうもの。だから幼い頃から「自信がなさそうに見られる」なんてコンプレックスを持っている人は、損をすることが多かったり、相手に真意が伝わりづらくて辛かったりしたことも少なくないかもしれないですね。だけど安心してください。自信がありそうに見せる!…それは話し方の工夫で随分変えられることがわかってきているのです。
アメリカの心理学者であるジャック・ブレームらによる研究(1975年)では、どのような話し方が「自信なく、不安げ」に見えてしまうのかということを、72名の大学生に320人の前でスピーチをしてもらい、それぞれの説得力を評定するという調査をしています。被験者にしてもらうスピーチの原稿は全く同じものです。さて、どのような話し方が「自信なし」と判定されてしまったのでしょうか。
それは大きく分けて2つのグループに分類されることがわかってきました。まず1つ目は、皆さんにも想像つきやすいと思うのですが、(A)「声に元気がない」「腕組みや脚組が頻繁」「視線の位置が定まらずにキョロキョロ」「話すときの姿勢が悪い」などのネガティブ要因が揃っている人たちでした。そりゃあ、声や視線がソワソワしていたら話も嘘っぽく聞こえてしまいますよね。

話が流暢すぎるのも、逆にアヤしい印象に!?
しかし、なんと意外だったのはもう一方のグループ。それは、(B)「早口」「澱みなく流暢」「話の間に間を置かない」「聴講者全員に対して情熱的」「やや興奮気味に話をする」という性質を備えているグループだったのです。このようなグループも、「自信なし」と評価されたのです。それどころか、(B)の流暢群は、(A)のソワソワ群以上に、なんと信頼性を低く評価され、しかも話が嘘っぽいとさえ判定される人も数多くいたのです。前のめりになってベラベラと激論するのも、自信のなさの表れだと、人は感じるものなんですね。ということは、この(A)と(B)のどちらにも極端に当てはまらないように気を付けることが肝心です。
特に(B)の流暢群は、ポーランド出身の社会学者であるソロモン・E・アッシュの研究(1956年)においても説得力が低い上に、なんと援助もされにくいことが明らかになっています。例えば会議などでは「あ、今ベラベラと語りすぎていないかな。自分のペースでまくし立てていないかな」ということを意識するだけでも随分変わってきます。そのようなときは、とにかく意識的に会話の速度をスローダウンしましょう。その方が自信があるように見えますし、話のスピードにメリハリがある方が魅力的に見えるという研究もあるのです。
これは私自身が試してみたことですが、自分の講演会の録音をしておいて、その後、自分が話すスピードを分析してみたり、自ら話す速度をコントロールをして、敢えてゆっくり話すようにしてみることで、だいぶ自信のある話しぶりが身に付くようになってきました。「話が上手い」というのと、「話に真実味がある」ということは全く違うことなのですね。
また、ルーマニア出身の社会心理学者であるセルジュ・モスコヴィッシらの研究(1980年)によると、自信がないという感情は、集団のなかで「自分はマイノリティ(少数派)だ」と思いすぎている状況で起きやすいこともわかっています。自分の話がメジャーなんだと思い込んでいる人は、ただそれだけで自信を持って話しやすいのです。なので、集団を前に話をするときは、次の2つがおすすめです。
(1)自分には「ここで意見を述べる権利」がある、メジャーなのは自分の考え方のはずだと言い聞かせること。
(2)集団の中で「この人は自分に共感してくれそう」という人を見つけて、まずはその人にわかってもらおうとすること。
具体的に、あがり症で悩んでいる人への訓練法として、集団の前で話をするときには、とにかく、なんとなくでも「味方」になってくれそうな人を短時間でパパっと見つけるという練習があります。会場にいる全員に話しかけて、全員を納得させようとするのではなく、まずは味方っぽいマイルドな人だけに伝わればいいや!という心持で話し始める。この心がけだけでも、「自分はマイノリティではない」「少数でも、こんなに傾聴してくれている人がいる」という感覚を取り戻して、無駄に緊張することなく、次第にリラックス感を回復することができるようになりますよ。
Photo by pixta
さて、次回は「物事を新しい視点で見てみよう、ポジティブになれる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
自信がなさそうに見える人ってどんな人? ビジネスに役立つ心理学

説得力を感じる人と信憑性を問われる人。その違いは?
何気ない話をしている時にも「この人は説得力がある」と感じるときと、反対に「この人はなんとなく信憑性がない」と思わされるときがありますよね。一般的に、自信を持って話す人には説得力を感じやすいものですが、自信がなさそうに見える人はせっかく良い内容を話していても「うーん。本当に?」と疑われやすい傾向があります。なぜなら、話し手本人が自信を持って堂々として見えるときは、聞く側にも「じゃあ一旦は相手を信用してみようか」というモチベーションが働きやすくなります。心理学では、これを動機エンハンシングといいます。
しかし、話し手本人に自信がなさそうな場合は、「え?この人大丈夫なのかしら」と聞く方を不安にさせてしまうもの。だから幼い頃から「自信がなさそうに見られる」なんてコンプレックスを持っている人は、損をすることが多かったり、相手に真意が伝わりづらくて辛かったりしたことも少なくないかもしれないですね。だけど安心してください。自信がありそうに見せる!...それは話し方の工夫で随分変えられることがわかってきているのです。
アメリカの心理学者であるジャック・ブレームらによる研究(1975年)では、どのような話し方が「自信なく、不安げ」に見えてしまうのかということを、72名の大学生に320人の前でスピーチをしてもらい、それぞれの説得力を評定するという調査をしています。被験者にしてもらうスピーチの原稿は全く同じものです。さて、どのような話し方が「自信なし」と判定されてしまったのでしょうか。
それは大きく分けて2つのグループに分類されることがわかってきました。まず1つ目は、皆さんにも想像つきやすいと思うのですが、(A)「声に元気がない」「腕組みや脚組が頻繁」「視線の位置が定まらずにキョロキョロ」「話すときの姿勢が悪い」などのネガティブ要因が揃っている人たちでした。そりゃあ、声や視線がソワソワしていたら話も嘘っぽく聞こえてしまいますよね。

話が流暢すぎるのも、逆にアヤしい印象に!?
しかし、なんと意外だったのはもう一方のグループ。それは、(B)「早口」「澱みなく流暢」「話の間に間を置かない」「聴講者全員に対して情熱的」「やや興奮気味に話をする」という性質を備えているグループだったのです。このようなグループも、「自信なし」と評価されたのです。それどころか、(B)の流暢群は、(A)のソワソワ群以上に、なんと信頼性を低く評価され、しかも話が嘘っぽいとさえ判定される人も数多くいたのです。前のめりになってベラベラと激論するのも、自信のなさの表れだと、人は感じるものなんですね。ということは、この(A)と(B)のどちらにも極端に当てはまらないように気を付けることが肝心です。
特に(B)の流暢群は、ポーランド出身の社会学者であるソロモン・E・アッシュの研究(1956年)においても説得力が低い上に、なんと援助もされにくいことが明らかになっています。例えば会議などでは「あ、今ベラベラと語りすぎていないかな。自分のペースでまくし立てていないかな」ということを意識するだけでも随分変わってきます。そのようなときは、とにかく意識的に会話の速度をスローダウンしましょう。その方が自信があるように見えますし、話のスピードにメリハリがある方が魅力的に見えるという研究もあるのです。
これは私自身が試してみたことですが、自分の講演会の録音をしておいて、その後、自分が話すスピードを分析してみたり、自ら話す速度をコントロールをして、敢えてゆっくり話すようにしてみることで、だいぶ自信のある話しぶりが身に付くようになってきました。「話が上手い」というのと、「話に真実味がある」ということは全く違うことなのですね。
また、ルーマニア出身の社会心理学者であるセルジュ・モスコヴィッシらの研究(1980年)によると、自信がないという感情は、集団のなかで「自分はマイノリティ(少数派)だ」と思いすぎている状況で起きやすいこともわかっています。自分の話がメジャーなんだと思い込んでいる人は、ただそれだけで自信を持って話しやすいのです。なので、集団を前に話をするときは、次の2つがおすすめです。
(1)自分には「ここで意見を述べる権利」がある、メジャーなのは自分の考え方のはずだと言い聞かせること。
(2)集団の中で「この人は自分に共感してくれそう」という人を見つけて、まずはその人にわかってもらおうとすること。
具体的に、あがり症で悩んでいる人への訓練法として、集団の前で話をするときには、とにかく、なんとなくでも「味方」になってくれそうな人を短時間でパパっと見つけるという練習があります。会場にいる全員に話しかけて、全員を納得させようとするのではなく、まずは味方っぽいマイルドな人だけに伝わればいいや!という心持で話し始める。この心がけだけでも、「自分はマイノリティではない」「少数でも、こんなに傾聴してくれている人がいる」という感覚を取り戻して、無駄に緊張することなく、次第にリラックス感を回復することができるようになりますよ。
Photo by pixta
さて、次回は「物事を新しい視点で見てみよう、ポジティブになれる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
- アイシティTOP
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 自信がなさそうに見える人ってどんな人? ビジネスに役立つ心理学