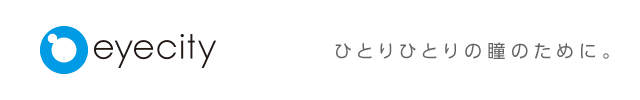- コンタクトレンズのアイシティ トップ
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 物事を新しい視点で見てみよう、ポジティブになれる心理学
心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 心理学者 / 臨床心理士
- 植木理恵
物事を新しい視点で見てみよう、ポジティブになれる心理学

偏見が不安やうつ、怒りなどのマイナス感情を生み出す
アメリカの心理学者アーロン・ベックは膨大なカウンセリングの研究を通して、不安やうつ、怒りといったネガティブな気持ちに振り回されやすい人に、ある共通点を発見しました。それはどんなことかというと…物事の捉え方が独特で、偏っており、合理的でないということ。ベックはそれを「認知バイアス」と呼び、心理療法の対象として重視しました。
確かに人はロボットのように物事を客観的にキャッチすることは難しいですね。人は何かを見たり聞いたりするときには、知らず知らずのうちに主観に基づく偏見を持っています。つまり心を通して、物事を見てしまうもの。それが人間らしさであり、その人の個性や感性を生み出す原動力ともなるのです。ただし、もしもそのせいで心がネガティブに陥ってしまうのだとしたら、それは控えた方がハッピーですよね。偏見のせいでいつも不安だったり、落ち込んだりしてしまうのはもったいないことです。特に次の3つの心理には要注意。(1)「拡大解釈」、(2)「自己関連づけ」、(3)「感情の重視」。あなたは大丈夫でしょうか?
まず(1)「拡大解釈」について。例えば、たまたま「恋人が電話に出ない」ということがあったとします。そのときに、一瞬で頭の中がいろんなことで埋め尽くされて、必要以上に落ち込むといった心のクセです。「そういえばこの間遅刻してきた」「ため息ついてた」「他の人と仲良くしていた」などと、「電話に出ない」こととは無関係なことを次々と思い浮かべる。するとだんだん不安な気持ちになってきます。さらに「そういえば友だちのSさんからの返信も遅い」「あのときのNさんからの返事もまだない」といった、もはや恋人と無関係なことまでも拡大鏡で探すように集めたりする心の偏りのことです。
この偏りに気づかないで放置していると、些細な偶然の出来事でも、いちいち「自分は価値がないんだ」「本当はみんなに嫌われているんだ」といった大げさな落ち込み方をしたり、自尊感情が傷つきやすくなるわけです。実際には恋人はぐっすり寝ていて、電話に気づかないだけかもしれないのに。拡大解釈を通して、物事を見ると、とにかく心が疲れます。
次に(2)「自己関連づけ」について。例えば「ここはミスだから、訂正した方が良いよ」と同僚に言われたり、上司に「この資料は間違えているからやり直しです」と指摘されたりしたとします。そのようなときに、それはあくまでも仕事上の問題であることを逸脱して、「私って能力低いんだ」「自分は信用されてない!」というように、人間性の問題にいちいち関連づけて悩むクセのことです。これも心が疲れるし、不毛なことですよね。「公」の問題を「私」の問題と混同して考えると、どんな事柄をも自分を否定するように感じられてきて、自己愛が傷つきやすくなります。その結果、怒りやうつ気分に支配されてしまうのです。仕事は仕事、あなたはあなた。そう考えるクセを持つ方が合理的なことがほとんどです。自己関連づけのクセを控えて、とにかく目前の仕事をクールにこなすほうが、メンタルは元気でいられます。

自分で自分を追い詰めていないか、セルフチェックしよう
最後に(3)「感情の重視」について。たとえば「明日は大事な用があって朝早いのに、眠れない」ということもありますよね。そのようなときに「こんなに眠れないってことは、自分は緊張して興奮して舞い上がっている」などと、余計な感情分析をしてしまうクセのことです。
自分の感情に敏感なのは大事なことですが、それが過剰になると、「こんなに興奮しているということは、明日は落ち着きのない日になる」「こんなにドキドキしているということは、明日は何か危険なことがある」というように、自分の中に湧き起こる感情を起点にして、この先に起きることを勝手に予測し、予言者のように断定して、それが自分をネガティブ感情へと追いやってしまうわけです。「今」の感情から「未来」を予言して、勝手に辛くなる。これを無意識にやっている人は実は少なくありません。でも、それは非合理的な考え方で、自分の未来をいつも暗雲立ち込める不安だらけのものにしてしまう、自分をいじめる心のクセといえます。
聞いたことがある方も多いと思いますが「認知療法」は、これらのような無数の考え方の偏り(認知バイアス)をクライアントに自覚してもらい、物の捉え方をもっと合理的でハッピーなものへと導くことを目指す心理療法です。セラピーでは、ネガティブな考え方について、(1)その考え方にエビデンス(根拠・裏づけ)はあるのか? (2)他の考え方はできないか? (3)そう考えることにどんな意味があるのか?ということをカウンセラーとともに考えます。
しかしカウンセリングに行かなくても、自分自身でもある程度ケアができます。「今、変な考え方をしていないかな?」「自分をいじめる考え方をしていないかな?」とチェックしたり、心がけてみたりする。それだけでも無駄なネガティブ感情を遠ざけるのには大きな効果があります。なので「ネガティブ感情から抜けられない」「ストレスを感じやすい」と漠然と悩んでいるタイプの方は、まずは、今日ご紹介した「拡大解釈」「自己関連づけ」「感情の重視」のクセを通して、自分で自分を苦しめていないか、1日1回はセルフチェックしてみることをおすすめします。
Photo by pixta
さて、次回は「あなたはインドア? アウトドア? 趣味に見る性格の心理学」についてお教えします。お楽しみに!
物事を新しい視点で見てみよう、ポジティブになれる心理学

偏見が不安やうつ、怒りなどのマイナス感情を生み出す
アメリカの心理学者アーロン・ベックは膨大なカウンセリングの研究を通して、不安やうつ、怒りといったネガティブな気持ちに振り回されやすい人に、ある共通点を発見しました。それはどんなことかというと...物事の捉え方が独特で、偏っており、合理的でないということ。ベックはそれを「認知バイアス」と呼び、心理療法の対象として重視しました。
確かに人はロボットのように物事を客観的にキャッチすることは難しいですね。人は何かを見たり聞いたりするときには、知らず知らずのうちに主観に基づく偏見を持っています。つまり心を通して、物事を見てしまうもの。それが人間らしさであり、その人の個性や感性を生み出す原動力ともなるのです。ただし、もしもそのせいで心がネガティブに陥ってしまうのだとしたら、それは控えた方がハッピーですよね。偏見のせいでいつも不安だったり、落ち込んだりしてしまうのはもったいないことです。特に次の3つの心理には要注意。(1)「拡大解釈」、(2)「自己関連づけ」、(3)「感情の重視」。あなたは大丈夫でしょうか?
まず(1)「拡大解釈」について。例えば、たまたま「恋人が電話に出ない」ということがあったとします。そのときに、一瞬で頭の中がいろんなことで埋め尽くされて、必要以上に落ち込むといった心のクセです。「そういえばこの間遅刻してきた」「ため息ついてた」「他の人と仲良くしていた」などと、「電話に出ない」こととは無関係なことを次々と思い浮かべる。するとだんだん不安な気持ちになってきます。さらに「そういえば友だちのSさんからの返信も遅い」「あのときのNさんからの返事もまだない」といった、もはや恋人と無関係なことまでも拡大鏡で探すように集めたりする心の偏りのことです。
この偏りに気づかないで放置していると、些細な偶然の出来事でも、いちいち「自分は価値がないんだ」「本当はみんなに嫌われているんだ」といった大げさな落ち込み方をしたり、自尊感情が傷つきやすくなるわけです。実際には恋人はぐっすり寝ていて、電話に気づかないだけかもしれないのに。拡大解釈を通して、物事を見ると、とにかく心が疲れます。
次に(2)「自己関連づけ」について。例えば「ここはミスだから、訂正した方が良いよ」と同僚に言われたり、上司に「この資料は間違えているからやり直しです」と指摘されたりしたとします。そのようなときに、それはあくまでも仕事上の問題であることを逸脱して、「私って能力低いんだ」「自分は信用されてない!」というように、人間性の問題にいちいち関連づけて悩むクセのことです。これも心が疲れるし、不毛なことですよね。「公」の問題を「私」の問題と混同して考えると、どんな事柄をも自分を否定するように感じられてきて、自己愛が傷つきやすくなります。その結果、怒りやうつ気分に支配されてしまうのです。仕事は仕事、あなたはあなた。そう考えるクセを持つ方が合理的なことがほとんどです。自己関連づけのクセを控えて、とにかく目前の仕事をクールにこなすほうが、メンタルは元気でいられます。

自分で自分を追い詰めていないか、セルフチェックしよう
最後に(3)「感情の重視」について。たとえば「明日は大事な用があって朝早いのに、眠れない」ということもありますよね。そのようなときに「こんなに眠れないってことは、自分は緊張して興奮して舞い上がっている」などと、余計な感情分析をしてしまうクセのことです。
自分の感情に敏感なのは大事なことですが、それが過剰になると、「こんなに興奮しているということは、明日は落ち着きのない日になる」「こんなにドキドキしているということは、明日は何か危険なことがある」というように、自分の中に湧き起こる感情を起点にして、この先に起きることを勝手に予測し、予言者のように断定して、それが自分をネガティブ感情へと追いやってしまうわけです。「今」の感情から「未来」を予言して、勝手に辛くなる。これを無意識にやっている人は実は少なくありません。でも、それは非合理的な考え方で、自分の未来をいつも暗雲立ち込める不安だらけのものにしてしまう、自分をいじめる心のクセといえます。
聞いたことがある方も多いと思いますが「認知療法」は、これらのような無数の考え方の偏り(認知バイアス)をクライアントに自覚してもらい、物の捉え方をもっと合理的でハッピーなものへと導くことを目指す心理療法です。セラピーでは、ネガティブな考え方について、(1)その考え方にエビデンス(根拠・裏づけ)はあるのか? (2)他の考え方はできないか? (3)そう考えることにどんな意味があるのか?ということをカウンセラーとともに考えます。
しかしカウンセリングに行かなくても、自分自身でもある程度ケアができます。「今、変な考え方をしていないかな?」「自分をいじめる考え方をしていないかな?」とチェックしたり、心がけてみたりする。それだけでも無駄なネガティブ感情を遠ざけるのには大きな効果があります。なので「ネガティブ感情から抜けられない」「ストレスを感じやすい」と漠然と悩んでいるタイプの方は、まずは、今日ご紹介した「拡大解釈」「自己関連づけ」「感情の重視」のクセを通して、自分で自分を苦しめていないか、1日1回はセルフチェックしてみることをおすすめします。
Photo by pixta
さて、次回は「あなたはインドア? アウトドア? 趣味に見る性格の心理学」についてお教えします。お楽しみに!
- アイシティTOP
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 物事を新しい視点で見てみよう、ポジティブになれる心理学