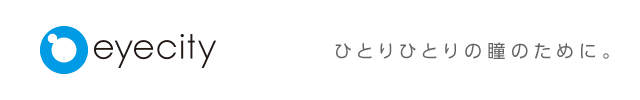- コンタクトレンズのアイシティ トップ
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 人が目をそらすのはなぜ? 視線回避の心理学
心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 心理学者 / 臨床心理士
- 植木理恵
人が目をそらすのはなぜ? 視線回避の心理学

人が視線を外したくなるときの心の動きとは?
会話をしているときに、「ふと視線を外す」「瞳の位置が何だか定まらない」「正面にいても、終始目を合わせずに話したがる」…私たちは、時々そのような人に出会うことがあります。「目を合わせる」という行為は、単に「分かりたい」「伝えたい」という能動的な意思表示だと考えられますが、目をそらす・視線を避けるという行為は、実はもう少し複雑です。一体どのような心の動きを意味しているのでしょうか。
この話をするために、心理学における「接近‐回避理論」について、簡単に説明しましょう。これはすべての生物の行動を、「報酬がある」と認識したら接近し、「罰がある」と認識したら回避するという単純行動により、一貫して説明しようとするシンプルな考え方です。動物を例にすると、エサがあれば近寄るし、電気ショックがあれば逃げる…という単純な行動理論ですね。しかし、人間という生き物はもっと複雑です。なぜなら、近くに来て話をしながらも(接近)、目だけはそらしたりする(回避)わけですから。相容れない行動をミックスするのは人間特有の心理だと思います。
では、接近しながらも回避するという行動に潜んでいる心理は、何なのでしょうか。精神分析学では、それは人間特有の心の「葛藤」であると考えます。葛藤とは、たとえば「この人と話をしたいけれど、自分には魅力がない」という過剰な自意識や、「あの人と仲良くなりたいから、たとえ嘘でも良い所を見せたい」といった虚栄心、「質問をしたいけれど、バカにされたくない」という羞恥心、「活躍したいけれど、失敗が怖い」といった不安などから沸き起こってくる、本人さえ無意識的である心の状態のことです。

ポジティブな理由で目をそらす人もいる
それでは、このような葛藤を抱えているとき、人はなぜ視線をそらすのでしょうか。これは、生後3ヶ月の赤ちゃんを対象とした研究によって明らかになってきました。一般的に赤ちゃんはお母さんが大好きですが、赤ちゃんがお母さんの顔を見ている時間と、人形の顔を見ている時間を比べたら、なんと、お母さんよりも人形を見ている時間の方が長いことが分かったのです。しかも、お母さんの顔を見ているとき、赤ちゃんはドキドキしていて、脈拍数・心拍数が上昇することも明らかになりました。イキイキと動き・表情が変化する人間の顔は、それがたとえ大好きなお母さんの顔であっても、生後間もない赤ちゃんにとっては情報処理に負担が掛かる可能性があります。その結果、お母さんの顔からあえて目をそらすことで、実は頭を休めているのではないかと、発達心理学では考えられているのです。
また生後8ヶ月~1歳4ヶ月の赤ちゃんにおいても、刺激を処理したり、興奮を落ち着かせたりするときに、「目をそらす」ことが1つの対応策であると報告されています。実は、赤ちゃんは泣き出す前から実際に泣くまで、ジェットコースターのように脈拍数・心拍数がガーッと高まることが分かっています。つまり、心臓に負担が掛かり過ぎないように、「目をそらす」「泣く」という方法で自分をプロテクトしているのです。これは大人であっても、当てはまりそうなメカニズムではないでしょうか。先に挙げたような様々な葛藤を抱えるとき、相手とがっちり目を合わせて話し続けるのは、ストレスが掛かり過ぎるというわけ。よって、ストレスや興奮の原因となる対象から目をそらすことで、上手く情動を調整する役割を果たしているのです。そしてそれは、単に「相手が嫌いだから目を合わせない」といったネガティブな要因というよりはむしろ、「なんとか自分のメンタルをコントロールしながら、相手と会話を続けたい」というポジティブな要因が多分に含まれています。このことを理解すれば、目をそらしてしまう癖に悩む人も、視線を避けられることに不快感を覚える人も、「これは自然な反応なのだ」と受け止められるのではないでしょうか。人は視線を合わせたり、視線を外したり、両方を上手く使い分けることで情動をコントロールして、コミュニケーションを取り続けているのです。
ですから、「目を合わせて話をするべき」というがんじがらめの考えからは脱却しましょう。いろいろな視線の使い方で、人はメンタルコントロールをしていると理解することで、会話をすることがもっと楽になり、子どもでも大人でも、自由に、そして豊かにディスカッションができるようになるはずです。
Photo by pixta
さて、次回は「注射のときは目を閉じた方が良い? 視覚と痛みにまつわる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
人が目をそらすのはなぜ? 視線回避の心理学

人が視線を外したくなるときの心の動きとは?
会話をしているときに、「ふと視線を外す」「瞳の位置が何だか定まらない」「正面にいても、終始目を合わせずに話したがる」…私たちは、時々そのような人に出会うことがあります。「目を合わせる」という行為は、単に「分かりたい」「伝えたい」という能動的な意思表示だと考えられますが、目をそらす・視線を避けるという行為は、実はもう少し複雑です。一体どのような心の動きを意味しているのでしょうか。
この話をするために、心理学における「接近‐回避理論」について、簡単に説明しましょう。これはすべての生物の行動を、「報酬がある」と認識したら接近し、「罰がある」と認識したら回避するという単純行動により、一貫して説明しようとするシンプルな考え方です。動物を例にすると、エサがあれば近寄るし、電気ショックがあれば逃げる…という単純な行動理論ですね。しかし、人間という生き物はもっと複雑です。なぜなら、近くに来て話をしながらも(接近)、目だけはそらしたりする(回避)わけですから。相容れない行動をミックスするのは人間特有の心理だと思います。
では、接近しながらも回避するという行動に潜んでいる心理は、何なのでしょうか。精神分析学では、それは人間特有の心の「葛藤」であると考えます。葛藤とは、たとえば「この人と話をしたいけれど、自分には魅力がない」という過剰な自意識や、「あの人と仲良くなりたいから、たとえ嘘でも良い所を見せたい」といった虚栄心、「質問をしたいけれど、バカにされたくない」という羞恥心、「活躍したいけれど、失敗が怖い」といった不安などから沸き起こってくる、本人さえ無意識的である心の状態のことです。

ポジティブな理由で目をそらす人もいる
それでは、このような葛藤を抱えているとき、人はなぜ視線をそらすのでしょうか。これは、生後3ヶ月の赤ちゃんを対象とした研究によって明らかになってきました。一般的に赤ちゃんはお母さんが大好きですが、赤ちゃんがお母さんの顔を見ている時間と、人形の顔を見ている時間を比べたら、なんと、お母さんよりも人形を見ている時間の方が長いことが分かったのです。しかも、お母さんの顔を見ているとき、赤ちゃんはドキドキしていて、脈拍数・心拍数が上昇することも明らかになりました。イキイキと動き・表情が変化する人間の顔は、それがたとえ大好きなお母さんの顔であっても、生後間もない赤ちゃんにとっては情報処理に負担が掛かる可能性があります。その結果、お母さんの顔からあえて目をそらすことで、実は頭を休めているのではないかと、発達心理学では考えられているのです。
また生後8ヶ月~1歳4ヶ月の赤ちゃんにおいても、刺激を処理したり、興奮を落ち着かせたりするときに、「目をそらす」ことが1つの対応策であると報告されています。実は、赤ちゃんは泣き出す前から実際に泣くまで、ジェットコースターのように脈拍数・心拍数がガーッと高まることが分かっています。つまり、心臓に負担が掛かり過ぎないように、「目をそらす」「泣く」という方法で自分をプロテクトしているのです。これは大人であっても、当てはまりそうなメカニズムではないでしょうか。先に挙げたような様々な葛藤を抱えるとき、相手とがっちり目を合わせて話し続けるのは、ストレスが掛かり過ぎるというわけ。よって、ストレスや興奮の原因となる対象から目をそらすことで、上手く情動を調整する役割を果たしているのです。そしてそれは、単に「相手が嫌いだから目を合わせない」といったネガティブな要因というよりはむしろ、「なんとか自分のメンタルをコントロールしながら、相手と会話を続けたい」というポジティブな要因が多分に含まれています。このことを理解すれば、目をそらしてしまう癖に悩む人も、視線を避けられることに不快感を覚える人も、「これは自然な反応なのだ」と受け止められるのではないでしょうか。人は視線を合わせたり、視線を外したり、両方を上手く使い分けることで情動をコントロールして、コミュニケーションを取り続けているのです。
ですから、「目を合わせて話をするべき」というがんじがらめの考えからは脱却しましょう。いろいろな視線の使い方で、人はメンタルコントロールをしていると理解することで、会話をすることがもっと楽になり、子どもでも大人でも、自由に、そして豊かにディスカッションができるようになるはずです。
Photo by pixta
さて、次回は「注射のときは目を閉じた方が良い? 視覚と痛みにまつわる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
- アイシティTOP
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 人が目をそらすのはなぜ? 視線回避の心理学