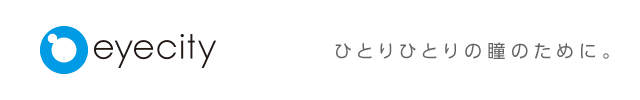- コンタクトレンズのアイシティ トップ
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 「ギャップがある人がモテる」は本当? 見た目と中身の心理学
心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 心理学者 / 臨床心理士
- 植木理恵
「ギャップがある人がモテる」は本当? 見た目と中身の心理学

ギャップ萌えを狙うには、自分を知ることが必要
不良キャラの男子が子猫にエサをあげている! お嬢様キャラの女子が足組みしてタバコを吸っている!…このような意外性が醸し出すインパクトのことをアニメでは「ギャップ萌え」なんていいますよね。では、現実の社会ではどうでしょう。やはりギャップがある人ほど、モテるのでしょうか?
心理学の観点からは、これは条件付きで「YES」といえそうです。それはどんな条件かというと、
(1)「ゲイン(=gain)効果」が働いていること
(2)「中心的特性」が働いていること
の2つです。まず(1)の「ゲイン効果」ですが、これは獲得効果とも呼ばれ、初めは悪い印象だったのに、ある日を境にして、良い印象に変わると、「本当はすごく素敵な人だった!」という驚きを覚え、その発見が後々の記憶にまで強い印象を残す現象です。
たとえば、今までメールでしかやり取りをしていない相手が、返信が遅い上にそっけない文しか送ってこないため、「もしかしたら意地悪な人? やる気もない?」とすごく悪い印象を持っていたとします。でも実際に会ってみたら、その相手がユーモアに溢れていて、熱意と誠実さに満ちた人だった。そのようなとき、大逆転の「ものすごく良い印象」が引き起こされますよね。よってギャップによる好印象は数十年経っても、頭から離れなくなる威力を持つと考えられています。もしかしたら、モテる人はこれを知らず知らずに実践しているのかもしれません。まさに「ツンデレ」というように、最初は相手に「そっけない人」「怖い人」「退屈な人」など、負のイメージを少しだけ持たせておき、別の日にはそれを覆すような逆のイメージを強調するということです。もしこの作戦を意図的にやっている人がいるとしたら、きっと周囲に小悪魔的な魅力を醸し出していることでしょう。
それを実践するには、メタ認知(自分で自分のことを俯瞰すること)をかなり強く意識する必要があります。「自分は人からどう見えているのか?」ということを客観視して、敢えてその部分と反対の良いイメージに覆す工夫をするわけですから。たとえば、あなた自身が「自分はプライドが高いヤツだと周囲に煙たがられている」というメタ認知をしたとしたら、早速それを覆す工夫をしてみましょう。次の機会には自分の失敗談を披露してみるとか、悩み事を打ち明けてみるといった、自己開示にトライするということです。自分で自分のイメージを覆すのは勇気がいることかもしれませんが、同じ行動を漫然と取り続けるよりも、自分の印象が悪い所を探して、そこを良く変える工夫をし続ける方が、「あれ? 本当はすごく素敵な人だった!」と周囲を長期的に驚かせることができ、仕事からも人からも、モテモテになるチャンスが増えるはずです。

ひとは、他人に対して温かい印象を求めている
それから条件(2)の「中心的特性」について。これはアメリカの社会心理学者ソロモン・アッシュが提唱した概念ですが、一言でいうと「ひとが求めるのは『温かい』という印象だ」ということです。アッシュはいろいろな印象形成の実験を行なった結果として、ひとは「温かい」「冷たい」という印象に最も左右されるという結果を導きました。では、どのようなことが他人に対して温かさを強調するのでしょうか? それは「私は自分のためではなく、誰かのために頑張ることが好き」ということを発信すること。向社会的な性格を、ひとは温かいと感じるからです。
私の場合は、自身を「心理学者」と言うよりも、「カウンセラー」と言う方がモテに近づくはずです。その方が人の悩みを解決したいという社会性を帯びて、温かいという印象を与えられるからです。その他の例で考えてみると、消防隊やレスキュー隊、看護師、介護士といった職業も、万人に対して温かさを連想させると思われます。ポイントは「自分のためより、人のため」という情報がどのくらいあるかということ。なので、学校や職場などで「私はこうしたい」「自分にはこの権利がある」という自分の欲求ばかり主張している人は、自ら「温かさ」という印象を遠ざけて、損をしている可能性があります。面接や営業でも、自分の思いを一方的に語り尽くしてしまうと、「このひとは熱心だけど、結局は自分の心を閉じていて冷たい」と悪い印象を植え付ける危険性があるわけです。
温かさを発信できる人になるために、「自分はこんな風にみんなの役に立てたら嬉しい」「仲間にこんな素敵なことをもたらしたい」といった相手目線のグッドニュースを、常に5つくらいは心に用意しておくことをお勧めします。温かいと思われることこそが、ひとの記憶に留まり、説得力を持ち、ひいては、モテるという好循環に入ることができる一番の近道だからです。
Photo by pixta
さて、次回は「『見て覚える』は効果的? 勉強にまつわる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
「ギャップがある人がモテる」は本当? 見た目と中身の心理学

ギャップ萌えを狙うには、自分を知ることが必要
不良キャラの男子が子猫にエサをあげている! お嬢様キャラの女子が足組みしてタバコを吸っている!...このような意外性が醸し出すインパクトのことをアニメでは「ギャップ萌え」なんていいますよね。では、現実の社会ではどうでしょう。やはりギャップがある人ほど、モテるのでしょうか?
心理学の観点からは、これは条件付きで「YES」といえそうです。それはどんな条件かというと、
(1)「ゲイン(=gain)効果」が働いていること
(2)「中心的特性」が働いていること
の2つです。まず(1)の「ゲイン効果」ですが、これは獲得効果とも呼ばれ、初めは悪い印象だったのに、ある日を境にして、良い印象に変わると、「本当はすごく素敵な人だった!」という驚きを覚え、その発見が後々の記憶にまで強い印象を残す現象です。
たとえば、今までメールでしかやり取りをしていない相手が、返信が遅い上にそっけない文しか送ってこないため、「もしかしたら意地悪な人? やる気もない?」とすごく悪い印象を持っていたとします。でも実際に会ってみたら、その相手がユーモアに溢れていて、熱意と誠実さに満ちた人だった。そのようなとき、大逆転の「ものすごく良い印象」が引き起こされますよね。よってギャップによる好印象は数十年経っても、頭から離れなくなる威力を持つと考えられています。もしかしたら、モテる人はこれを知らず知らずに実践しているのかもしれません。まさに「ツンデレ」というように、最初は相手に「そっけない人」「怖い人」「退屈な人」など、負のイメージを少しだけ持たせておき、別の日にはそれを覆すような逆のイメージを強調するということです。もしこの作戦を意図的にやっている人がいるとしたら、きっと周囲に小悪魔的な魅力を醸し出していることでしょう。
それを実践するには、メタ認知(自分で自分のことを俯瞰すること)をかなり強く意識する必要があります。「自分は人からどう見えているのか?」ということを客観視して、敢えてその部分と反対の良いイメージに覆す工夫をするわけですから。たとえば、あなた自身が「自分はプライドが高いヤツだと周囲に煙たがられている」というメタ認知をしたとしたら、早速それを覆す工夫をしてみましょう。次の機会には自分の失敗談を披露してみるとか、悩み事を打ち明けてみるといった、自己開示にトライするということです。自分で自分のイメージを覆すのは勇気がいることかもしれませんが、同じ行動を漫然と取り続けるよりも、自分の印象が悪い所を探して、そこを良く変える工夫をし続ける方が、「あれ? 本当はすごく素敵な人だった!」と周囲を長期的に驚かせることができ、仕事からも人からも、モテモテになるチャンスが増えるはずです。

ひとは、他人に対して温かい印象を求めている
それから条件(2)の「中心的特性」について。これはアメリカの社会心理学者ソロモン・アッシュが提唱した概念ですが、一言でいうと「ひとが求めるのは『温かい』という印象だ」ということです。アッシュはいろいろな印象形成の実験を行なった結果として、ひとは「温かい」「冷たい」という印象に最も左右されるという結果を導きました。では、どのようなことが他人に対して温かさを強調するのでしょうか? それは「私は自分のためではなく、誰かのために頑張ることが好き」ということを発信すること。向社会的な性格を、ひとは温かいと感じるからです。
私の場合は、自身を「心理学者」と言うよりも、「カウンセラー」と言う方がモテに近づくはずです。その方が人の悩みを解決したいという社会性を帯びて、温かいという印象を与えられるからです。その他の例で考えてみると、消防隊やレスキュー隊、看護師、介護士といった職業も、万人に対して温かさを連想させると思われます。ポイントは「自分のためより、人のため」という情報がどのくらいあるかということ。なので、学校や職場などで「私はこうしたい」「自分にはこの権利がある」という自分の欲求ばかり主張している人は、自ら「温かさ」という印象を遠ざけて、損をしている可能性があります。面接や営業でも、自分の思いを一方的に語り尽くしてしまうと、「このひとは熱心だけど、結局は自分の心を閉じていて冷たい」と悪い印象を植え付ける危険性があるわけです。
温かさを発信できる人になるために、「自分はこんな風にみんなの役に立てたら嬉しい」「仲間にこんな素敵なことをもたらしたい」といった相手目線のグッドニュースを、常に5つくらいは心に用意しておくことをお勧めします。温かいと思われることこそが、ひとの記憶に留まり、説得力を持ち、ひいては、モテるという好循環に入ることができる一番の近道だからです。
Photo by pixta
さて、次回は「『見て覚える』は効果的? 勉強にまつわる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
- アイシティTOP
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 「ギャップがある人がモテる」は本当? 見た目と中身の心理学