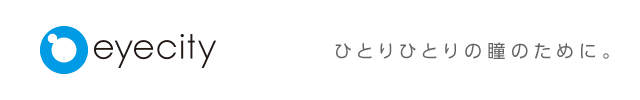- コンタクトレンズのアイシティ トップ
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 視覚と聴覚の相互作用? 目と音楽にまつわる心理学
心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 心理学者 / 臨床心理士
- 植木理恵
視覚と聴覚の相互作用? 目と音楽にまつわる心理学

耳にする音楽によって、目にする風景の印象は異なる
目に映る風景。そのときに流れている音楽。この2つがお互いに影響を与え合うことは、誰しも経験的に知っていることではないでしょうか。紺碧に晴れ渡った空を見上げていても、そのときにとても悲しい失恋ソングを耳にしていたら、どんな空も一気に涙色に見えてくるでしょう。その反対に、軽やかなポップスを聴きながら、同じ空を見上げたら、未来がどこまでも開けていくような開放感を感じるかもしれません。
この視覚と聴覚の関係。これは単なる「気のせい」なのでしょうか。いいえ、気のせいではないということを、心理学の実験が明らかにしています。この実験では、日常のありふれた風景の写真や映像、例えば「山並み」「夕焼け」「庭園」「道路」などをランダムに提示して、被験者に見てもらいます。そのときにBGMとして、誰しも聞き覚えのあるクラシック音楽(ショパンやベートーヴェン、モーツァルトなど)を流した場合、それらの写真や映像に対する被験者の印象はどう変わるのかを分析したのです。すると、当初の仮説よりも、かなり詳細なことが分かってきました。
たとえば、ベートーヴェンの『運命』を流しながら、「山並み」の写真を見せたところ、被験者には次のような変化が見られたのです。まず(1)として、高音のボリュームがずっと大きく、強弱差は小さめで安定している箇所を聞いているときは、その「山並み」の写真が「美しい」「ダイナミック」といった印象を強く持つこと。そして(2)、反対に高音のボリュームが抑え気味で低音メインの箇所を聴いているときには、同じ「山並み」の写真が「荘厳だ」「落ち着いている」といった印象に変わること。そして最後に、(3)高音域が不規則で華やかさがあり、低音域が規則的で単調な箇所で、同写真を見た際には「洗練されている」「洒落ている」と思いやすくなることが、多くの被験者に見られたのです。

日常生活に音楽の効用を活かしてみよう
他の曲で考えると、(1)は映画『ロッキーのテーマ』や広瀬香美『ロマンスの神様』のような感じで、(2)は映画『ゴッドファーザー 愛のテーマ』や中森明菜『難破船』、そして(3)はエディット・ピアフ『愛の賛歌』やイルカ『なごり雪』などが個人的には浮かびます。
ともかく、私たちは知らず知らずのうちに、BGMのテンポや音量、音域によって、目にする対象の印象を大きく変化させているということなんですね。このような音楽の効用を他に活かさない手はありません。普段、仕事のプレゼンテーションでクライアントに映像を見てもらうときや学校の授業でクラスメイトに学習内容を発表するとき、結婚式でスライドを披露するときには、見る人に対してどんな印象を持って欲しいかということを考えて、今日からBGMに、よりこだわってみてはいかがでしょうか。
またシーンとした静まり返った会議室や教室、病院も、ときには適切な音楽を用いることで、相手が認識する「視覚」の印象が大きく操作されます。その場所を「美しく」見せたいのか、「荘厳に」見せたいのか、はたまた「お洒落に」見せたいのか。その印象は耳から入る音楽に懸かっていることを意識してみるのも大切かもしれませんね。
Photo by pixta
さて、次回は「涙を我慢することの心理的影響は? 感情表現にまつわる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
視覚と聴覚の相互作用? 目と音楽にまつわる心理学

耳にする音楽によって、目にする風景の印象は異なる
目に映る風景。そのときに流れている音楽。この2つがお互いに影響を与え合うことは、誰しも経験的に知っていることではないでしょうか。紺碧に晴れ渡った空を見上げていても、そのときにとても悲しい失恋ソングを耳にしていたら、どんな空も一気に涙色に見えてくるでしょう。その反対に、軽やかなポップスを聴きながら、同じ空を見上げたら、未来がどこまでも開けていくような開放感を感じるかもしれません。
この視覚と聴覚の関係。これは単なる「気のせい」なのでしょうか。いいえ、気のせいではないということを、心理学の実験が明らかにしています。この実験では、日常のありふれた風景の写真や映像、例えば「山並み」「夕焼け」「庭園」「道路」などをランダムに提示して、被験者に見てもらいます。そのときにBGMとして、誰しも聞き覚えのあるクラシック音楽(ショパンやベートーヴェン、モーツァルトなど)を流した場合、それらの写真や映像に対する被験者の印象はどう変わるのかを分析したのです。すると、当初の仮説よりも、かなり詳細なことが分かってきました。
たとえば、ベートーヴェンの『運命』を流しながら、「山並み」の写真を見せたところ、被験者には次のような変化が見られたのです。まず(1)として、高音のボリュームがずっと大きく、強弱差は小さめで安定している箇所を聞いているときは、その「山並み」の写真が「美しい」「ダイナミック」といった印象を強く持つこと。そして(2)、反対に高音のボリュームが抑え気味で低音メインの箇所を聴いているときには、同じ「山並み」の写真が「荘厳だ」「落ち着いている」といった印象に変わること。そして最後に、(3)高音域が不規則で華やかさがあり、低音域が規則的で単調な箇所で、同写真を見た際には「洗練されている」「洒落ている」と思いやすくなることが、多くの被験者に見られたのです。

日常生活に音楽の効用を活かしてみよう
他の曲で考えると、(1)は映画『ロッキーのテーマ』や広瀬香美『ロマンスの神様』のような感じで、(2)は映画『ゴッドファーザー 愛のテーマ』や中森明菜『難破船』、そして(3)はエディット・ピアフ『愛の賛歌』やイルカ『なごり雪』などが個人的には浮かびます。
ともかく、私たちは知らず知らずのうちに、BGMのテンポや音量、音域によって、目にする対象の印象を大きく変化させているということなんですね。このような音楽の効用を他に活かさない手はありません。普段、仕事のプレゼンテーションでクライアントに映像を見てもらうときや学校の授業でクラスメイトに学習内容を発表するとき、結婚式でスライドを披露するときには、見る人に対してどんな印象を持って欲しいかということを考えて、今日からBGMに、よりこだわってみてはいかがでしょうか。
またシーンとした静まり返った会議室や教室、病院も、ときには適切な音楽を用いることで、相手が認識する「視覚」の印象が大きく操作されます。その場所を「美しく」見せたいのか、「荘厳に」見せたいのか、はたまた「お洒落に」見せたいのか。その印象は耳から入る音楽に懸かっていることを意識してみるのも大切かもしれませんね。
Photo by pixta
さて、次回は「涙を我慢することの心理的影響は? 感情表現にまつわる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
- アイシティTOP
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 視覚と聴覚の相互作用? 目と音楽にまつわる心理学