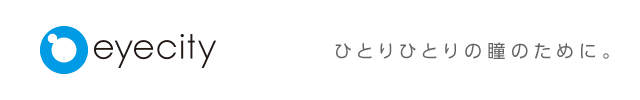- コンタクトレンズのアイシティ トップ
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 注射のときは目を閉じた方が良い? 視覚と痛みにまつわる心理学
心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 心理学者 / 臨床心理士
- 植木理恵
注射のときは目を閉じた方が良い? 視覚と痛みにまつわる心理学

筋肉の緊張度によって、注射の痛さが異なる
あなたは、病院で注射を打つときに思わず目を閉じてしまうタイプですか? それとも、注射針をじーっと見つめるタイプでしょうか? 私は後者ですが、「注射が痛い」「怖い」と感じるのは、筋肉が緊張していたり、心拍数が高まった状態に起きやすいとされています。では、そのような筋肉の緊張は、いつ起きるのかというと、それはその人の「性格」によって異なることが分かってきています。
簡単に分けると、(1)視覚処理をしない方が緊張せずに楽というタイプと、(2)きちんと視覚処理をする方が緊張せずに楽という2つのタイプになります。言い換えれば、前者は「知らぬが仏」タイプの人、後者は「知は力なり」タイプの人ともいえるかもしれません。認知心理学では、意味をあまり説明されずに問題解決をする方がリラックスできる人と、逆にあらかじめ意味を深く教えてもらわないと問題解決のモチベーションが上がらない人に分かれます。これは大人だけではなく、小学2年生を対象にした実験でも明らかになっていることです。
さて、あなたはどちらのタイプでしょうか。注射以外で例を挙げると、(1)の人は、病気になったらその詳細を知る必要はなくて、ただ専門家の判断に委ねたいという人、対人関係では同僚やパートナーの気持ちを突き詰めなくてもOKという人が当てはまると思います。何かを厳密に詮索するよりも、深く知らない方が気楽な人。臨床心理学の表現で言い換えると、グレーゾーンを許容できる人ということです。

性格による視覚的接触が、痛みの主観的感度と関連する!?
(2)はその逆で、病気に罹ったら、その説明を詳しく聞きたがったり、会社や学校での自分の評価を細かく把握したがる人。一体「白」なのか「黒」なのか、真実を知らずにはいられないというタイプです。つまり、グレーゾーンを許容するのが苦手な人。だから、自分で情報をしっかり見て、知っておいた方が、かえって気楽だということになります。よって、注射のときに目を閉じて見ない方が筋肉の緊張が起きないか、それともしっかり見届けた方が返って筋肉の緊張が起きないか、それは前述の性格の差によって異なるといえそうです。
またこの分類を超えて、一般的に痛みを減じる方法も複数提唱されています。まずは注射後に甘いものを食べると良いという説、また頭や肩などの皮膚を自分でさすると良いという説、さらに注射を担当する医療従事者の方とコミュニケーションを取ると良いという説です。確かに、「注射が苦手なんです」と伝えるのはもちろん、ただ「よろしくお願いします」というだけでも、ただ沈黙の中、注射を受けるより、リラックス度は違うはずです。これらの方法はおそらく、脳内の快楽ホルモンを分泌させることで痛みが軽減するだろうという考え方なのでしょう。
今後の医療において、患者の性格による視覚的接触が痛みの主観的感度と関連するということは注目されるべきことではないかと思います。また、ひとつの性格診断テストとして、目を閉じて注射を受けた方が痛くないか、それとも見ながら注射を受けた方が痛くないか、それによって自分の真の性格を知るというのも、案外楽しいことではないでしょうか。
Photo by pixta
さて、次回は「視覚と聴覚の相互作用? 目と音楽にまつわる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
注射のときは目を閉じた方が良い? 視覚と痛みにまつわる心理学

筋肉の緊張度によって、注射の痛さが異なる
あなたは、病院で注射を打つときに思わず目を閉じてしまうタイプですか? それとも、注射針をじーっと見つめるタイプでしょうか? 私は後者ですが、「注射が痛い」「怖い」と感じるのは、筋肉が緊張していたり、心拍数が高まった状態に起きやすいとされています。では、そのような筋肉の緊張は、いつ起きるのかというと、それはその人の「性格」によって異なることが分かってきています。
簡単に分けると、(1)視覚処理をしない方が緊張せずに楽というタイプと、(2)きちんと視覚処理をする方が緊張せずに楽という2つのタイプになります。言い換えれば、前者は「知らぬが仏」タイプの人、後者は「知は力なり」タイプの人ともいえるかもしれません。認知心理学では、意味をあまり説明されずに問題解決をする方がリラックスできる人と、逆にあらかじめ意味を深く教えてもらわないと問題解決のモチベーションが上がらない人に分かれます。これは大人だけではなく、小学2年生を対象にした実験でも明らかになっていることです。
さて、あなたはどちらのタイプでしょうか。注射以外で例を挙げると、(1)の人は、病気になったらその詳細を知る必要はなくて、ただ専門家の判断に委ねたいという人、対人関係では同僚やパートナーの気持ちを突き詰めなくてもOKという人が当てはまると思います。何かを厳密に詮索するよりも、深く知らない方が気楽な人。臨床心理学の表現で言い換えると、グレーゾーンを許容できる人ということです。

性格による視覚的接触が、痛みの主観的感度と関連する!?
(2)はその逆で、病気に罹ったら、その説明を詳しく聞きたがったり、会社や学校での自分の評価を細かく把握したがる人。一体「白」なのか「黒」なのか、真実を知らずにはいられないというタイプです。つまり、グレーゾーンを許容するのが苦手な人。だから、自分で情報をしっかり見て、知っておいた方が、かえって気楽だということになります。よって、注射のときに目を閉じて見ない方が筋肉の緊張が起きないか、それともしっかり見届けた方が返って筋肉の緊張が起きないか、それは前述の性格の差によって異なるといえそうです。
またこの分類を超えて、一般的に痛みを減じる方法も複数提唱されています。まずは注射後に甘いものを食べると良いという説、また頭や肩などの皮膚を自分でさすると良いという説、さらに注射を担当する医療従事者の方とコミュニケーションを取ると良いという説です。確かに、「注射が苦手なんです」と伝えるのはもちろん、ただ「よろしくお願いします」というだけでも、ただ沈黙の中、注射を受けるより、リラックス度は違うはずです。これらの方法はおそらく、脳内の快楽ホルモンを分泌させることで痛みが軽減するだろうという考え方なのでしょう。
今後の医療において、患者の性格による視覚的接触が痛みの主観的感度と関連するということは注目されるべきことではないかと思います。また、ひとつの性格診断テストとして、目を閉じて注射を受けた方が痛くないか、それとも見ながら注射を受けた方が痛くないか、それによって自分の真の性格を知るというのも、案外楽しいことではないでしょうか。
Photo by pixta
さて、次回は「視覚と聴覚の相互作用? 目と音楽にまつわる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
- アイシティTOP
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 注射のときは目を閉じた方が良い? 視覚と痛みにまつわる心理学