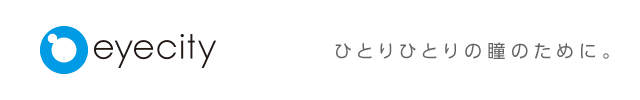- コンタクトレンズのアイシティ トップ
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 涙を我慢することの心理的影響は? 感情表現にまつわる心理学
心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 心理学者 / 臨床心理士
- 植木理恵
涙を我慢することの心理的影響は? 感情表現にまつわる心理学

泣くことは、心の浄化に繋がっている
あなたは涙を我慢した経験がありますか? 日本社会では、涙を流すこと=心の「弱さ」と思われてしまう風潮がありますよね。特に職場や学校では、いつも笑顔で、感情をコントロールできる人の方が成熟していると見なされる傾向があります。また大人になると子どもよりも泣きづらくなるし、男性は女性よりも泣きづらいといった文化も根強いかもしれません。しかし近年では、メンタルヘルスの観点から「感情表出の重要性」が認識されつつあります。つまり、ときには、我慢せずに涙を流すことが精神衛生上、とても有益であるという考え方も広まっているのです。
特に、「不安」「恐怖」「怒り」から来る涙は流せるものなら流すことが大切です。なぜなら泣くと、一気にストレスや緊張が和らぎ、心のバランスが平常に戻ることが、精神医学の知見からも明らかになっているからです。心理学では、涙は感情のカタルシス(浄化)と呼ばれています。だから私のクライアントがカウンセラーの前で涙をこぼすことがあったら、それは「人間的成長」が起きたからとか、カウンセリングの効果が出ているなどとポジティブに考えます。
泣くことをいつも我慢する人は、笑顔を作ることすら、次第にぎこちなくなっていくということが分かっています。つまり、喜怒哀楽の表現力そのものが乏しくなるのです。すると当然のことながら、他人とのコミュニケーションに無理が出てきたり、ストレスを感じやすくなりますよね。よって、一生を通して本人の幸福感が高いのは、他人の前で、涙を流すことを含めた感情表現を自然にできる人の方なんです。

豊かな人生のために、涙腺トレーニングを始めよう
私の調査では、喜怒哀楽を豊かに表現できる人の方が、主観的幸福度が高いばかりか、友人の数も生涯年収も多いというデータがあります。それはおそらく、感情を(ときには涙を)表す人の方が、周囲からの共感や気持ちの理解を得るチャンスが多いからです。また、「私が泣いたところで誰も気にしない」「自分なんかが涙したら嫌われる」、そう心に言い聞かせることは、自己肯定感や自己愛を痩せさせてしまうことにつながります。実際に、自分の感情を閉じ込め続けることで、うつ症状や不安障害のリスクが高まることも知られています。
ですから、あなたの人生をより豊かにするために、今日から少しずつ涙腺トレーニングを意識してみませんか。そのためには、次のようなことを工夫してみると、感情表現がしやすくなると考えられます。
(1)「涙=弱さ」という決めつけを自分はしていないか? また会社や学校など、自分が所属する集団の中にそのような決めつけが起きていないか? まずは、「人間は時に涙して当然だ」ということを、お互いに認めることが第一歩です。
(2)信頼できない人の前では、涙腺は固くなります。定期的に学生時代の幼なじみや親戚、恋人、時にはカウンセラーなど、心から開放感を持てる人と積極的に過ごす時間を増やしてみてください。
(3)たまには、ひとりで「しみじみ過去を振り返る時間」を作ることも大事。ネガティブな時間をしっかり習慣化できる人は、自分の感情整理をすることが上手くなります。その結果、涙や笑顔といった感情表現がスムーズになることが多いです。
(4)自分自身に向き合うことが難しい場合、ひとりで「泣けるドラマ」「泣ける漫画」「泣けるドキュメンタリー」等に没頭し、「自分だって涙が出るんだな」ということを体感してください。
時には人前で、ときにはひとりでハラハラと涙を流して、もっと感情表現がしなやかになると良いですね。そして本当の意味で、屈強なメンタルを手に入れましょう。
Photo by pixta
さて、次回は「なぜ悪夢を見るの? 睡眠と夢にまつわる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
涙を我慢することの心理的影響は? 感情表現にまつわる心理学

泣くことは、心の浄化に繋がっている
あなたは涙を我慢した経験がありますか? 日本社会では、涙を流すこと=心の「弱さ」と思われてしまう風潮がありますよね。特に職場や学校では、いつも笑顔で、感情をコントロールできる人の方が成熟していると見なされる傾向があります。また大人になると子どもよりも泣きづらくなるし、男性は女性よりも泣きづらいといった文化も根強いかもしれません。しかし近年では、メンタルヘルスの観点から「感情表出の重要性」が認識されつつあります。つまり、ときには、我慢せずに涙を流すことが精神衛生上、とても有益であるという考え方も広まっているのです。
特に、「不安」「恐怖」「怒り」から来る涙は流せるものなら流すことが大切です。なぜなら泣くと、一気にストレスや緊張が和らぎ、心のバランスが平常に戻ることが、精神医学の知見からも明らかになっているからです。心理学では、涙は感情のカタルシス(浄化)と呼ばれています。だから私のクライアントがカウンセラーの前で涙をこぼすことがあったら、それは「人間的成長」が起きたからとか、カウンセリングの効果が出ているなどとポジティブに考えます。
泣くことをいつも我慢する人は、笑顔を作ることすら、次第にぎこちなくなっていくということが分かっています。つまり、喜怒哀楽の表現力そのものが乏しくなるのです。すると当然のことながら、他人とのコミュニケーションに無理が出てきたり、ストレスを感じやすくなりますよね。よって、一生を通して本人の幸福感が高いのは、他人の前で、涙を流すことを含めた感情表現を自然にできる人の方なんです。

豊かな人生のために、涙腺トレーニングを始めよう
私の調査では、喜怒哀楽を豊かに表現できる人の方が、主観的幸福度が高いばかりか、友人の数も生涯年収も多いというデータがあります。それはおそらく、感情を(ときには涙を)表す人の方が、周囲からの共感や気持ちの理解を得るチャンスが多いからです。また、「私が泣いたところで誰も気にしない」「自分なんかが涙したら嫌われる」、そう心に言い聞かせることは、自己肯定感や自己愛を痩せさせてしまうことにつながります。実際に、自分の感情を閉じ込め続けることで、うつ症状や不安障害のリスクが高まることも知られています。
ですから、あなたの人生をより豊かにするために、今日から少しずつ涙腺トレーニングを意識してみませんか。そのためには、次のようなことを工夫してみると、感情表現がしやすくなると考えられます。
(1)「涙=弱さ」という決めつけを自分はしていないか? また会社や学校など、自分が所属する集団の中にそのような決めつけが起きていないか? まずは、「人間は時に涙して当然だ」ということを、お互いに認めることが第一歩です。
(2)信頼できない人の前では、涙腺は固くなります。定期的に学生時代の幼なじみや親戚、恋人、時にはカウンセラーなど、心から開放感を持てる人と積極的に過ごす時間を増やしてみてください。
(3)たまには、ひとりで「しみじみ過去を振り返る時間」を作ることも大事。ネガティブな時間をしっかり習慣化できる人は、自分の感情整理をすることが上手くなります。その結果、涙や笑顔といった感情表現がスムーズになることが多いです。
(4)自分自身に向き合うことが難しい場合、ひとりで「泣けるドラマ」「泣ける漫画」「泣けるドキュメンタリー」等に没頭し、「自分だって涙が出るんだな」ということを体感してください。
時には人前で、ときにはひとりでハラハラと涙を流して、もっと感情表現がしなやかになると良いですね。そして本当の意味で、屈強なメンタルを手に入れましょう。
Photo by pixta
さて、次回は「なぜ悪夢を見るの? 睡眠と夢にまつわる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
- アイシティTOP
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 涙を我慢することの心理的影響は? 感情表現にまつわる心理学