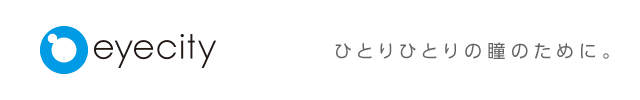- コンタクトレンズのアイシティ トップ
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 騙されにくくなれば、何事も圧倒的に有利になる! 嘘をついている人を見抜く心理学
心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 心理学者 / 臨床心理士
- 植木理恵
騙されにくくなれば、何事も圧倒的に有利になる! 嘘をついている人を見抜く心理学

人間はなぜ嘘をつくの?
人は4歳くらいになると、誰しも小さな嘘をつくようになります。嘘をつくのは、あまり望ましいことではありませんが、心理学ではコミュニケーション能力や言語能力がうまく発達してきている証しとしてとらえます。
本来ならば、ピュアな心ですべてを正直に伝えることが理想なはず。でも現実には、家族、友だち、恋人、職場の人など人間関係が広くなるにつれて、「嘘をつかないと、かえって人を傷つけてしまう」「嘘を言わないと、かえって問題がややこしくなる」という経験を味わうことも増えてきます。実は、大学生を対象にした調査では、誰しも一日に7、8回は、無意識にコミュニケーションの中に嘘を潜ませることが分かっています。

嘘には種類がある!?
嘘には、「嘘も方便」という罪の軽いものから、「嘘つきは泥棒の始まり」という犯罪につながってしまうような非常識なものまで幅がありますが、心理学では、この軽重を含めて欺瞞(ぎまん)的コミュニケーションと言います(※欺瞞とは、人をあざむくこと、騙すこと)。この欺瞞的コミュニケーションには、次の2種類があります。
(1)本当はないものを、「ある」という嘘
(2)本当はあるものを、「ない」とかき消す嘘
(1)は、本当はどこにも出かけていないのに「バカンスで海外に行ってきた」。本当は恋愛経験がないのに「デートが多くて忙しい」。というように、いわゆる見栄をはるタイプの嘘。それに対して(2)は、本当はよく知っている情報なのに「私は何も聞いていない」と知らん顔をしたり、本当はAさんと付き合っているのに「Aさんとは会ったこともない」と言ったりするように、何かを隠すタイプの嘘のことです。
私たちは、この(1)と(2)を上手に使い分けながら、欺瞞を含んだコミュニケーションによって、うまく人間関係をやりくりしているわけです。しかも、20代~40代の男女を対象にした調査では、(1)も(2)もほとんどバレずに済んでいることが分かっています。いわば欺瞞が横行している状態ですね。
このように人間関係を維持したり、お互いの幸福感を高めたりする上では、嘘はある程度必要なものかもしれません。つまり、コミュニケーションにおける嘘を心理学的な側面から考えてみると、嘘はあながち極悪なものとは決められなさそうです。

目は口ほどに物を言う!? 嘘の見破り方
しかし一方で、これらの欺瞞的コミュニケーションを見破ることについての研究も重ねられています。口ではどんなに上手に嘘をついても、やはり「まばたき」「視線の動き」など目の表情には、しっぽを表してしまうようです。
簡単にまとめると、次のような傾向が分かってきています。
(1)ないものを「ある」と言うとき、目はあまり動かない
(2)あるものを「ない」と言うとき、目の動きは活発になる
つまり、見栄をはるような作り話をしているときには瞳は堂々としているけど、何かを隠そうと必死になっているときには瞳はおどおどするということですね。
たしかに、作り話をしている人は、たとえば「ハワイでこんなことがあった」「こんなラブレターをもらった」などと作り話をしながら、次第に自分も自分の言葉に酔いしれて、嘘をついていることを心のどこかで忘れてしまいます。まるで自分が自分に騙されるような攪乱した嘘をついているときには意外と本人は自己嫌悪感も小さく、その結果、表情にも表れにくい。
一方で、「ある」ことを隠そうとしている人は、「本当は自分が見聞きしたことがある」という現実をリアルに肌で感じておきながら、それがバレないように芝居をしているわけですから、頭の中は大忙し。動揺が大きいため、それが瞳にも表れやすいのです。
どうしても本当か嘘かを追求してみたいときには、この(1)(2)の原理を使ってみましょう。
たとえば、相手がAさんと会っていたのかを知りたいというとき。「昨日は何をしていた?」とざっくり聞くと、相手が嘘をつく場合、好きなように話を作りやすい。つまり作り話をする(1)の状況になり、本音が瞳には現れません。しかし、「昨日Aさんと会っていた?」とストレートに聞くと、会ってなかったという嘘をつくときには(2)の状況となり、途端に表情が変わりやすくなるはずです。
「会っていない」と言いながら瞳が堂々として動かないのなら、実際に会ってはいないのでしょう。瞳の動きで嘘を見破りたいというときには、「○○があったんじゃないの?」「××を知っているでしょう?」とはっきり聞いて、相手に否定させ、そのときのまばたきや視線の動きを観察すると一目瞭然というわけです。
このように、心と表情の関係性を知っておくと、いざという大事な決断の際、ヒントになるかもしれませんね。
Photo by pixta
さて次回は、「左よりも右にいる人の方が魅力的に見える? 視線の動きにまつわる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
騙されにくくなれば、何事も圧倒的に有利になる! 嘘をついている人を見抜く心理学

人間はなぜ嘘をつくの?
人は4歳くらいになると、誰しも小さな嘘をつくようになります。嘘をつくのは、あまり望ましいことではありませんが、心理学ではコミュニケーション能力や言語能力がうまく発達してきている証しとしてとらえます。
本来ならば、ピュアな心ですべてを正直に伝えることが理想なはず。でも現実には、家族、友だち、恋人、職場の人など人間関係が広くなるにつれて、「嘘をつかないと、かえって人を傷つけてしまう」「嘘を言わないと、かえって問題がややこしくなる」という経験を味わうことも増えてきます。実は、大学生を対象にした調査では、誰しも一日に7、8回は、無意識にコミュニケーションの中に嘘を潜ませることが分かっています。

嘘には種類がある!?
嘘には、「嘘も方便」という罪の軽いものから、「嘘つきは泥棒の始まり」という犯罪につながってしまうような非常識なものまで幅がありますが、心理学では、この軽重を含めて欺瞞(ぎまん)的コミュニケーションと言います(※欺瞞とは、人をあざむくこと、騙すこと)。この欺瞞的コミュニケーションには、次の2種類があります。
(1)本当はないものを、「ある」という嘘
(2)本当はあるものを、「ない」とかき消す嘘
(1)は、本当はどこにも出かけていないのに「バカンスで海外に行ってきた」。本当は恋愛経験がないのに「デートが多くて忙しい」。というように、いわゆる見栄をはるタイプの嘘。それに対して(2)は、本当はよく知っている情報なのに「私は何も聞いていない」と知らん顔をしたり、本当はAさんと付き合っているのに「Aさんとは会ったこともない」と言ったりするように、何かを隠すタイプの嘘のことです。
私たちは、この(1)と(2)を上手に使い分けながら、欺瞞を含んだコミュニケーションによって、うまく人間関係をやりくりしているわけです。しかも、20代~40代の男女を対象にした調査では、(1)も(2)もほとんどバレずに済んでいることが分かっています。いわば欺瞞が横行している状態ですね。
このように人間関係を維持したり、お互いの幸福感を高めたりする上では、嘘はある程度必要なものかもしれません。つまり、コミュニケーションにおける嘘を心理学的な側面から考えてみると、嘘はあながち極悪なものとは決められなさそうです。

目は口ほどに物を言う!? 嘘の見破り方
しかし一方で、これらの欺瞞的コミュニケーションを見破ることについての研究も重ねられています。口ではどんなに上手に嘘をついても、やはり「まばたき」「視線の動き」など目の表情には、しっぽを表してしまうようです。
簡単にまとめると、次のような傾向が分かってきています。
(1)ないものを「ある」と言うとき、目はあまり動かない
(2)あるものを「ない」と言うとき、目の動きは活発になる
つまり、見栄をはるような作り話をしているときには瞳は堂々としているけど、何かを隠そうと必死になっているときには瞳はおどおどするということですね。
たしかに、作り話をしている人は、たとえば「ハワイでこんなことがあった」「こんなラブレターをもらった」などと作り話をしながら、次第に自分も自分の言葉に酔いしれて、嘘をついていることを心のどこかで忘れてしまいます。まるで自分が自分に騙されるような攪乱した嘘をついているときには意外と本人は自己嫌悪感も小さく、その結果、表情にも表れにくい。
一方で、「ある」ことを隠そうとしている人は、「本当は自分が見聞きしたことがある」という現実をリアルに肌で感じておきながら、それがバレないように芝居をしているわけですから、頭の中は大忙し。動揺が大きいため、それが瞳にも表れやすいのです。
どうしても本当か嘘かを追求してみたいときには、この(1)(2)の原理を使ってみましょう。
たとえば、相手がAさんと会っていたのかを知りたいというとき。「昨日は何をしていた?」とざっくり聞くと、相手が嘘をつく場合、好きなように話を作りやすい。つまり作り話をする(1)の状況になり、本音が瞳には現れません。しかし、「昨日Aさんと会っていた?」とストレートに聞くと、会ってなかったという嘘をつくときには(2)の状況となり、途端に表情が変わりやすくなるはずです。
「会っていない」と言いながら瞳が堂々として動かないのなら、実際に会ってはいないのでしょう。瞳の動きで嘘を見破りたいというときには、「○○があったんじゃないの?」「××を知っているでしょう?」とはっきり聞いて、相手に否定させ、そのときのまばたきや視線の動きを観察すると一目瞭然というわけです。
このように、心と表情の関係性を知っておくと、いざという大事な決断の際、ヒントになるかもしれませんね。
Photo by pixta
さて次回は、「左よりも右にいる人の方が魅力的に見える? 視線の動きにまつわる心理学」についてお教えします。お楽しみに!
- アイシティTOP
- 心理学者 植木理恵の瞳にまつわる心理学
- 騙されにくくなれば、何事も圧倒的に有利になる! 嘘をついている人を見抜く心理学